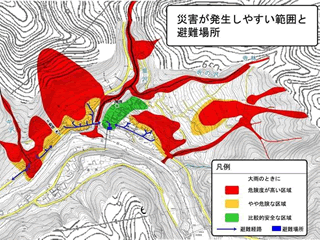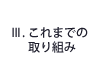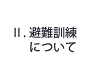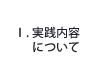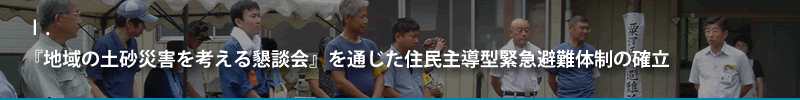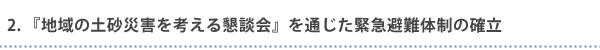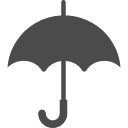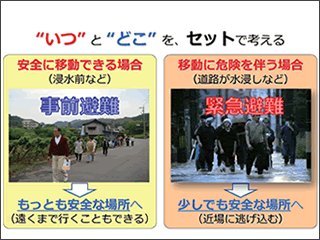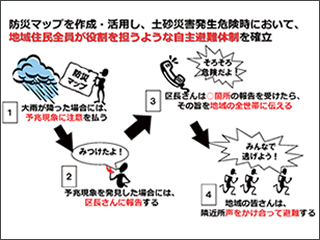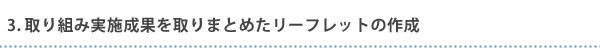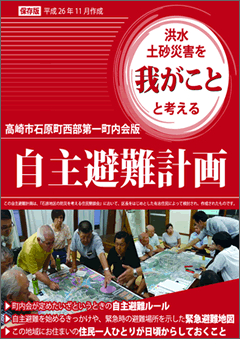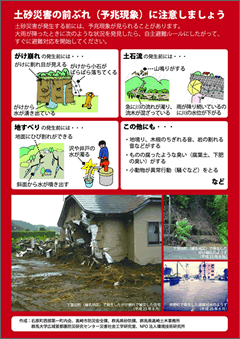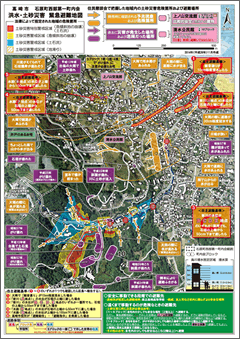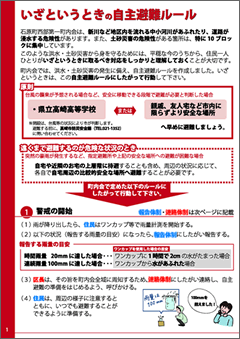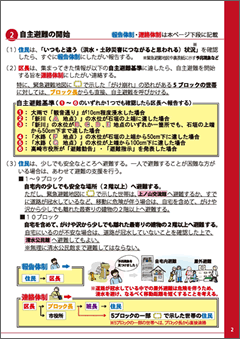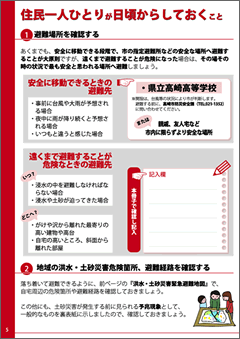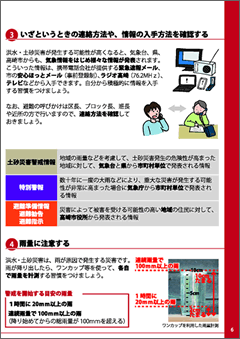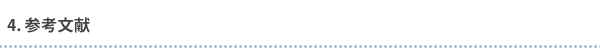平成13年の土砂災害防止法の施行により、急傾斜地や土石流危険地域については、土砂災害警戒区域に指定し、開発行為の制限や緊急避難体制の整備を行うことになりました。
特に土砂災害による犠牲者の減少のためには,緊急避難体制を整備し、地域住民の適切な避難を促すことが求められます。そして、緊急避難体制を構築し、それが活用されるためには、地域住民の主体的な参加が必要不可欠となります。
そこで、本研究室では、土砂災害危険地域に居住する住民の方に地域の土砂災害リスクを理解してもらうとともに、地域の安全を確保するために緊急避難体制を確立することを促すためのリスク・コミュニケーションを実践しています。
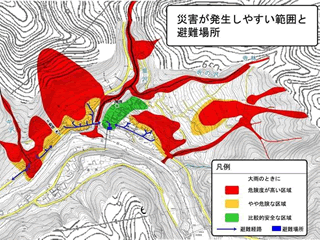 |
土砂災害警戒区域図の例
(H16年度みなかみ町粟沢地区) |
上記のような問題意識のもと、本研究室では、地域住民主導型の自主避難体制の確立を目的とした取り組みを実施しています。
この懇談会を通じて、以下のような地域独自の緊急避難体制の構築を目指しています。
雨が降り始めたら、地域住民全員が周辺の様子に注意し、
いつもと違う状況になったら、みんなで声をかけあって、
自主的に避難することのできる仕組みをつくる!
このような仕組みの構築を促すために、懇談会では以下のような点について地域住民の理解を得ながら、地域住民とともに具体的な避難ルールの検討を行っています。
地域住民の中には、「防災は行政がやるべきこと」という意識、すなわち防災対応に関して行政に依存している方も少なくありません。しかし、行政に依存した防災対応では、被害軽減に限界があることは明らかです。
そのため、懇談会の冒頭で、土砂災害対策の難しさや予測情報の不確実性などについて理解を深めてもらうとともに、そのような土砂災害に地域住民自らで備えていこうとする主体性を持つことを促します。
 |
懇談会で説明している様子
(H24年度渋川市豊秋地区) |
土砂災害の予測情報は、その発生メカニズムの複雑さやその発生素因である局所的な豪雨の予測精度の不確かさなどにより、十分とはいえません。そのため、行政からの災害情報や避難情報を待っているだけでは逃げ遅れてしまう可能性があります。しかし、その一方で、多くの土砂災害危険地域には過去の被災経験によって言い伝えられた地域固有の予兆現象などが存在します。
そこで、懇談会では、それら地域固有の予兆現象に関する情報を地域で共有するために、懇談会参加住民に、『過去に災害が発生した場所やそのときの様子』や『大雨が降ったときに見られる現象』などを地域の地図に書き込んでいく作業をしてもらいます。
 |
地図に危険箇所を書き込んでいる様子
(H24年度沼田市下川田地区) |
災害から避難するためには、少なくとも「いつ」「どこ」に避難するのかを具体的に決めておく必要があります。
「いつ」については、先に挙げてもらった地域内の土砂災害危険箇所(予兆現象)を用いて、避難開始タイミングを検討しています。
具体的には、以下のようなルールを検討しています。
『地域内で “◯個” の予兆現象の発生が確認された場合』
避難を開始するタイミングとして、地域内で発生が確認された予兆現象の個数を決めておく
『地域内の “この現象” が確認された場合』
その現象が確認されたらすぐに避難を開始するための基準として、地域内である特定の予兆現象を決めておく

避難開始タイミングを検討する際、住民の方には、あいまいな基準とせずに、具体的な基準を決めるように促しています。その理由として、地域内の誰か(区長や町会長、自主防災会長など)の判断が必要となるようなあいまいな基準にしておくと、いざというときにその方が避難開始の判断を躊躇してしまった場合に避難が遅れてしまいう可能性があること、また個人に判断の責任を負わせることにつながってしまうことを指摘しています。
そこで、避難開始タイミングは、平常時に地域住民全員で具体的な基準をつくっておき、いざというときには、その基準を運用するだけにすることを促しています。
また、ここで検討した基準以外でも、 “いつもと違う状況になりそうだ” と判断されるような状況であった場合には、さらに早い段階で自主避難を促すことの重要性も合わせて伝えていきます。
 |
地図を囲んで避難開始タイミングを検討している様子
(H24年度安中市横川地区) |

「どこ」に避難するのかについては、避難を開始する際の周辺の状況に応じて、少なくとも2つの避難場所を検討してもらうことを促しています。

一つは、『早期避難時の避難場所』です。
今後災害の発生が危惧される状況ではあるものの、まだ避難場所への移動に危険が伴わない状況で避難を開始する場合には、『遠くでもよいので、安全な場所』を避難場所として決めてもらいます。土砂災害の危険がない地域外や堅牢な建物(学校など)などがこれに該当します。
もう一つは、『緊急一時避難場所』です。
避難の開始が遅れたり、急激な事態の進展による避難を開始しようとした際に、すでにいつ災害が発生してもおかしくない状況になってしまった場合には、『自宅周辺で少しでも安全な場所』を避難場所として決めてもらいます。公共の建物だけでなく、民間の建物や近所の住民宅、また場合によっては自宅にとどまることも選択肢の一つとして、命の危険を最小限にすることのできる場所を検討してもらいます。
また、『緊急一時避難場所』の検討の際には、このような避難は100%の安全を担保するものではないので、可能な限り早期の避難を心がけることの重要性も合わせて伝えていきます。
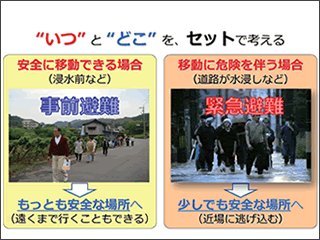 |
| 2種類の避難について |
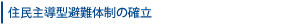
懇談会を通じて検討してきた上記の内容を地域の避難ルールとして、取りまとめていきます。ここで検討する地域の避難ルールは、地域住民全員が参加することを前提としたものです。その理由は、いざというときに自分一人で避難の判断をしようとすると、「まだ大丈夫だろう」「これまで災害はなかったから」などと事態の緊迫性を正しく認識することができず、その結果、避難の開始が遅れてしまう可能性があるためです。
また、地域の状況を特定に人間だけで把握しようとするのではなく、地域住民全員がセンサーとなって、それぞれの自宅周辺の様子に注意することで、地域全体の状況を把握することにより、地域全体で災害に対峙するという地域づくりを目指しているためです。
具体的なルールは、以下の通りです。

大雨が降った場合には、予兆現象に注意を払う
雨が強くなってきたら、地域住民全員で、自宅周辺の様子に注意する。この際、地域の雨量を目安にするために、コップなどを用いた簡易の雨量計測をすることも推奨しています。
予兆現象を発見した場合には、区長さんに報告する
自宅周辺でいつもと違う状況が発生していることを確認した住民は、すぐに区長など予め決めておいた地域の代表者に報告する。
報告内容が予め決めておいた避難開始基準に達した場合、すぐに全世帯に伝える
区長などの代表者は、地域住民からの報告内容が予め決めていた避難開始基準に達した場合には、すぐにその旨を全世帯に伝え、自主避難の開始を促す。
地域住民は隣近所で声をかけ合って避難する
自主避難の連絡を受けた住民は、隣近所に声をかけ合って、周辺の状況に応じた避難場所へ避難する。
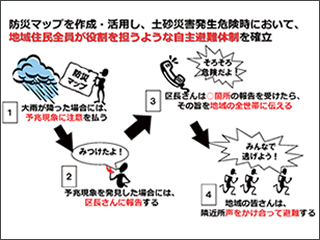 |
| 地域独自の避難ルールの概要 |
懇談会には、地域の多くの住民に参加を呼びかけて実施しますが、地域住民全員に参加してもらうことは不可能です。しかし、先に紹介したように、ここで検討する避難体制は地域住民全員が参加することが前提になります。
そこで、懇談会を通じて構築した緊急避難体制を地域住民に広く周知し、また取り組めたことを地域で継続して実践してもらうために、取り組み実施成果を取りまとめたリーフレットを作成しています。このリーフレットには、地域独自の避難ルール、土砂災害危険箇所や予兆現象等に関する情報を地図に取りまとめたものや、土砂災害に関する一般的な知識を記載しています。
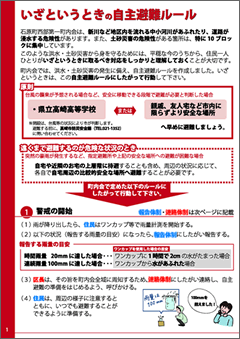 |
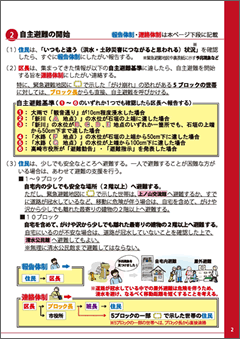 |
| |
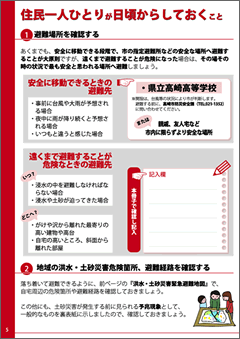 |
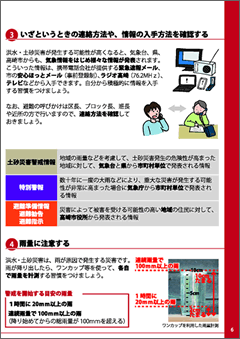 |
| リーフレット(防災マップ)の例 | H26年度高崎市石原地区 |