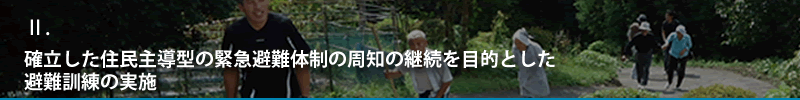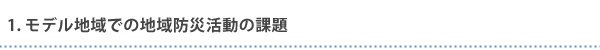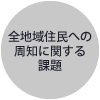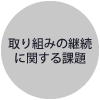ここで紹介したような、ある地域をモデルケースとして、専門家や地元自治体職員等が参画して、地域住民とともに行う実践(社会実験)は、防災に限らず様々な分野で全国的に行われています。しかし、これらの実践には、少なくとも二つの課題があると考えます。
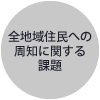 |
これらの取り組みには、地域住民全員が参加するわけではありません。参加者の多くは地域コミュニティの役員であったり、防災に関心の高い人です。そのため、取り組みに参加していない住民(たとえば、防災に関心の低い方)に対して、取り組みで検討した内容を周知する必要があります。 |
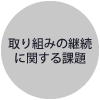 |
モデルケースとしての実践が終了してしまう、つまり、専門家や自治体職員からの支援がなくなってしまうと、地域住民だけでは活動が継続していない場合が少なくありません。本取組を通じて構築された地域独自の避難ルールを、地域のルールとして引き継いでいくためには、定期的な取り組みの継続は必要不可欠です。 |
そこで、本取組では、懇談会を通じて構築した地域独自の避難ルールに則った避難訓練を実施しています。
この訓練の目的は、構築した避難ルールの内容を確認するとともに、地域住民全員に参加を促すことで、『地域住民全員への周知』を図り、また定期的に開催することで、『取り組みの継続』を促すことを念頭においています。
避難訓練は、本番を想定して実施しなければ意味がありません。そのため、本訓練では、懇談会で検討した緊急避難の流れを全て確認します。
訓練開始の連絡を受けた住民は、コップなどを用いて、雨量の計測を行います。
※しかし、訓練当日に雨が降っているとは限りません。そのため、訓練実施補助員が、どこかの世帯のコップなどに水を入れにい
きます。
※水を入れる世帯を事前に告知せずに訓練を実施すれば、本番さながらの緊張感のある訓練になります。
 |
| 訓練実施補助員がコップなどに水を入れている様子 |

雨量が基準に達したことを確認した世帯(コップなどに水を入れられた世帯)は、リーダーに通報します。
 |
| 住民が、雨量が基準に達したことを確認した様子 |
基準の雨量に達した旨の通報を受けたリーダーは、警戒体制をとるように地域住民に連絡します。
 |
地域にある防災行政無線の屋外スピーカーを使用して
地域住民に連絡している様子 |
警戒体制をとるように指示を受けた住民は、自宅周辺の様子に注意します。
※といっても、訓練時に予兆現象が確認されるわけはありません。そのため、訓練実施補助員が、地域で作成した土砂災害警戒避難
地図に記された、予兆現象の発生予想箇所に看板を立てます。
※雨量計測同様、どこで予兆現象が発生するのかを事前に告知せずに、訓練を実施すれば、本番のような緊張感を持って訓練に取り
組んでもらえるものと期待されます。また、毎年、違う場所の予兆現象発生予想箇所に看板を立てることで訓練のマンネリ化を防
ぐことができると考えます。
 |
| 訓練補助員が看板を設置している様子 |

「いつもと違う何か(=看板)」を発見した住民は、リーダーに通報します。
 |
| 住民が看板を発見したときの様子 |
予兆現象に関する通報を受けたリーダーは、その通報内容が基準に達したら、
自主避難勧告を発表し、地域住民に避難を促します。
 |
携帯電話を使って、地域の役員に自主避難の開始を
地域住民に促すよう指示している様子 |
自主避難勧告の発表を受けた住民は、隣近所で声をかけ合って、予め決めておいた避難場所に避難します。
 |
| 住民が避難する様子 |

避難先ごとに、避難者を確認して、リーダーに報告する
 |
| 班ごとに避難者が集まっている様子 |