| 津波防災教育を実施するための授業時間を特別に用意しなくても、各学年の教科の中には、地震・津波・防災に関連する授業の内容があります。ここでは、それらの授業単元をピックアップするとともに、そこでどのような内容を児童・生徒に教えることができるのかを取りまとめました。また、授業で教える際に必要となる知識等については、資料を整理してありますので、そちらも参考にしてください。 | 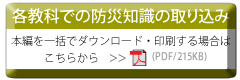 |
教 科 |
単 元 |
津波と関連する内容 |
算 数 |
[2年生] 14 長いものの長さとたんい |
・津波の高さを用いて問題作成 「津波の高さは釜石湾で3メートルになるらしいです。では、3メートルは何センチ?」 |
生 活 |
[上] みんななかよし がっこう たんけん こうてい たんけん |
・学校内のいろいろな場所にいるときに地震が発生したらどうするのかを教える。 |
[下] なかよしひろがれ もっとまちをしりたいね みんなでつかうばしょ みんなのためのくふう |
・避難場所や記念碑等、避難標識などをさがしてみる。 ・過去に津波がどこまできたのかを確認したり、絵地図づくりをしたりする。 |
|
体 育 |
[1・2年生] 着衣 |
・津波の高さを知る。 ・津波の速さと流れの強さを知る。 |
教 科 |
単 元 |
津波と関連する内容 |
国 語 |
[3年生] たから物をさがしに |
・「津波がきたら」という題材にした作文へ発展させる。 |
[4年生] つたえたいことははっきりさせて書こう 新聞記者になろう |
・津波に関する記事を例として用いる。 |
|
算 数 |
[3年生] 2 時こくと時間 時間のしくみを調べよう |
・津波の到達時間を用いて、単位の変換に関する問題をつくる。 「津波は何度もくるので,避難したら3時間はそのままじっとしていることが必要です。では、何分でしょうか?」 |
[3年生] 6 長いものの長さのはかり方 長さをはかろう |
・津波の長さを用いて、単位の変換に関する問題をつくる。 「津波は普通の波とちがって、長さが○キロメートルもあります。では、何メートルでしょうか?」 |
|
社 会 |
1 見つめてみよう わたしたちの まち 1. まちたんけんをしよう 3. ポスターや絵地図にまとめよう |
・避難場所や避難経路、石碑などの確認。 |
4 わたしたちの市はどんな所 |
・海と山にかこまれた釜石市、「おいしい魚はたくさんとれるけど、津波が来る」ということを教える。 |
|
5 安全なくらしとまちづくり |
・震災による火災の話から発展させて、今後釜石にも大きな地震が来ることを教える。 |
|
7 昔のくらしとまちづくり 1. 昔のくらし まちに残る昔を調べよう |
・過去の津波による被災状況やそれを今に伝える石碑等を教える。 |
8 わたしたちの県のまちづくり 3. 県の地図を広げて |
・沿岸地域の地形やその特徴として、地震や津波が多いことを教える。 |
教 科 |
単 元 |
津波と関連する内容 |
国 語 |
目的に応じた伝え方を考えよう ニュース番組作りの現場から |
・「ここでは有珠山の噴火をニュースにしたときのお話でしたが、津波がきたらどんな内容のニュースになるでしょうか?」といった感じで発展させる。 |
算 数 |
13 百分率とグラフ 比べ方を考えよう |
・宮地県沖地震などの今後発生する確率を用いて、問題をだす。 「○○地震は今後70%の確率で発生するといわれています。これを小数にしたらいくつ?」 |
理 科 |
5 台風と天気の変化 6 流れる水のはたらき |
・洪水や津波から街を守るための施設として、護岸工事や防潮堤工事がおこなわれていることを紹介する。 |
社 会 |
3 くらしを支える状況 |
・防災行政無線の役割、津波警報や注意報について教える。 |
4 住みよいくらしと環境 水産業のさかんな地域をたずねて |
・「海沿いで魚はたくさんとれていいけど、地震や津波の危険もある」ことを教える。 |
|
保 健 |
1 けがの防止 4. けがの手当て |
・地震がきたら、どんなけがをする可能性があるのか、またそれを防ぐためにはどうしたいいのかを考えさせる。 |
家 庭 |
作ってみよう,調べてみよう 2 作っておいしく食べよう 1. ごはんとみそ汁をつくってみよう |
・地震や津波が発生した場合には、“炊きだし”といって、避難場所で自分たちが食事をつくることが必要になることがあることを伝える。 ・調理実習中や料理中に地震が発生したときの対処方法を教える |
くふうしてみよう 2 快適な住まい方を考えてみよう 2. 課題を決めて,調べよう |
・活動例として、「地震から身を守るためのくふう」を考える。 |
教 科 |
単 元 |
津波と関連する内容 |
国 語 |
イーハトーブの夢 |
・宮沢賢治の生まれた年に、明治三陸地震が発生したことにふれ、その被害の様子を教える。 |
自分の考えを発信しよう |
・発展として、津波に関わる自分の考えをまとめ、発表してもらう。 |
|
算 数 |
5 単位あたりの大きさ 比べ方を考えよう 2. 速さの表し方 |
・津波の速さを例にした問題をつくる。 「津波は陸上では、秒速○メートルです。海岸から○メートル離れたA君の家まで、津波は何秒できますか?」 |
理 科 |
5 大地のつくりと変化 地しんによる大地の変化 |
・地震のしくみと被害の様子を教える。 ・地震の後には津波が来るということを確認する。 |
その他 |
・実験中に地震が発生した場合に起こりうる事故とその予防や対応の仕方を教える。 |
|
社 会 |
5 暮らしと政治を調べてみよう 1. 人々の願いとまちづくり |
・災害時の政治のはらたきとして、被災者支援等を教え、過去の震災の被害や復興までの道のりを教える。 ・地域の防災まちづくり活動を紹介する。 |
郷土史,釜石の歴史 |
・過去の津波被害を教える。 |
|
家 庭 |
よりよい生活をめざそう 地域とのつながりを広げよう 2. 自分にできることをやってみよう |
・地域の人から過去の津波被害を聞いてみる。 ・いざというときに、何ができるのかを考える。 |
教 科 |
単 元 |
津波と関連する内容 |
数 学 |
[1年生] 3章 1次方程式 2. 1次方程式の利用 |
・速さ、時間、道のりの問題を津波避難を例にして作成する。 「釜石湾では地震発生後30分で津波がやってくると想定されている。地震発生後、何分までに避難を開始すれば、無事に避難することができるでしょうか?」 |
[2年生] 2章 連立方程式 2. 連立方程式の利用 |
・速さ、時間、道のりの問題を津波避難を例にして作成する。 「避難する際に、おばあちゃんの家に寄っていくことにしました。無事に避難するためには、地震発生後、何分までに自宅を出発し、おばあちゃん宅から何分以内に避難しなければならないでしょうか?」 |
|
[3年生] 5章 相似な図形 |
・比率を求める問際を作成する。 「(建物と津波が写っている写真を用意し)建物の高さ○メートルである。このとき津波の高さは?」 |
[3年生] 5章 6章 三平方の定理 |
・避難距離に関する問題を作成する。 「地図上の直線距離だと○メートルである。しかし、自宅と避難場所には○メートルの標高差がある。避難する際の道のりは何メートルになるか?」 |
理 科 [2分野] |
第2編 第2章 ゆれる大地 |
・プレートテクトニクスに関連させて、津波の発生メカニズムや三陸沿岸で津波が多い理由を教える。 |
社 会 [地理] |
第2編 第1章 身近な地域の調査 ■学びの広場 地域の規模に応じた調査 |
・“釜石と津波”、“三陸沿岸と地震”などのテーマで調査の企画する。 |
第3編 第1章 世界と日本の自然環境 7. 自然災害とその対策 |
・対策として、釜石の湾港防波堤や緊急地震速報,避難勧告・指示などを教える。 |
|
社 会 [歴史] |
第6章 二度の世界大戦と日本 1. 第一次世界大戦 ⑥大衆文化の形成 |
・関東大震災の記述から、今後、災害が発生した際に起こりうる社会問題について教える。 |
社 会 [公民] |
第1章 わたしたちの暮らしと現代社会 2. 社会のなかで生きる ②家族と地域社会で支え合い |
・災害時には、高齢者や年少者を助けることが必要であることを教える。 |
保 健 |
3.傷害の防止 4. 自然災害に備えて 5. 応急手当の意義と手順 |
・災害発生時に起こりうるけがや、それを防止するための対策について教える。 ・救命救急法(心肺蘇生法,AEDなど)を教える。 |
家 庭 |
A.生活の自立と衣食住 5.快適に住まう 4. 自然とともに住まう |
・災害に対する家屋の安全対策(家具の固定など)や非常持ち出し品として用意しておくものを教える。 |
その他 |
・防災頭巾をつくる。・調理実習を炊き出し訓練としておこなう。 |
教 科 |
単元や津波と関連する内容 |
国 語 |
・読書についての発展学習で、津波に関する図書を読む ・津波関連図書を読み、作文活動や感想を書く ・レポートを書く学習で、津波や防災を題材とする ・津波や防災をテーマとした新聞づくり |
英 語 |
・Tsunamiに関する図書や資料をテキストとして用いる |
体 育 |
・着衣泳で、水中歩行の困難さを体験 |
道 徳 |
・生命の尊厳 ・郷土愛 ・田老万里の長城 ・稲むらの火 |
総 合 |
・津波パンフレット、防災マップづくり ・体験者からの聞き取り、地域の津波痕跡調査 ・演劇 |
特 別 活 動 |
・避難訓練 ・長期休み前の注意 |